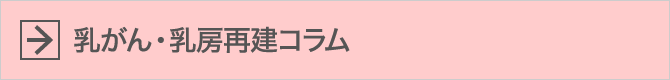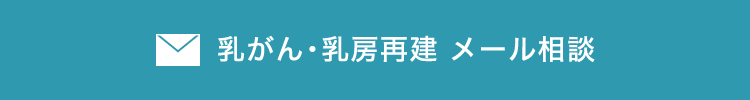補助療法(コラム)|南雲吉則医師が詳しく解説|ナグモクリニック 東京・名古屋・大阪・福岡
乳がん・乳房再建コラム
乳がん・乳房再建コラム(補助療法)
- 頭文字
- 抗がん剤はやりやすい
- ホルモン療法にはどのようなものがありますか?
- 補助療法による更新期障害
- タモキシフェンは子宮体がんになる?
- 術前抗がん剤と術後抗がん剤、いいのはどっち
- 抗がん剤の副作用はなぜ起こる
- 乳がんの予後因子
- 乳がん治療の新憲法
- オンコタイプDX
- 補助療法をするかどうかは自分で決めよう!
頭文字
アメリカ人は頭文字が好きです。
JFKならジョン・F・ケネディ。KFCはケンタッキーフライドチキン。YMOはイエロー・マジック・オーケストラ(それは日本か)。なんでも頭文字にする。
抗がん剤も頭文字であらわします。
- C
- シクロフォスファミドとかサイクロフォスファマイド。アルキル化剤という種類で商品名エンドキサンです。
- M
- メトトレキサート。代謝拮抗物質で商品名メトトレキセートです。
- F
- 5-フルオロウラシル。代謝拮抗物質で商品名5-FUです。
- A
- アドリアマイシン。抗がん性抗生物質のアントラサイクリン系で、商品名はアドリアシンです。
- E
- エピルビシン。抗がん性抗生物質のアントラサイクリン系で、商品名はファルモルビシンです。
- T
- ドセタキセルおよびパクリタキセル。植物アルカロイドのタキサン系で商品名はそれぞれタキソテールやタキソール。
いろいろな呼び方があってめんどうくさいですね。あなたがサイクロフォスファマイドといったときに医者がシクロフォスファミドといったからといって、赤面する必要はまったくありません。でもこうした煩わしさを解消するために頭文字を使うのです。
がんはどの抗がん剤が効くかはわからないので、いくつかの抗がん剤を組み合わせて、効果の増強と副作用の減少を図ります。これが多剤併用療法で、抗がん剤の頭文字を並べてCMF療法、CAF療法、CEF療法、AC療法、FAC療法、FEC療法、TC療法のように表現します。多くの場合は点滴で投与します。
抗がん剤は身体のダメージが大きいので、休みを取りながら一定間隔で繰り返します。この間隔が短いと身体が回復しませんし、長すぎるとがんが息を吹き返す可能性があるので、適切な間隔が決められています。休薬期間も含めた1回分の治療を1「クール」または1「サイクル」と呼びます。AC療法、FAC療法、FEC療法ならば3週に1回の投与が1クールです。
抗がん剤はやりやすい
がん撲滅は人類の永遠のテーマです。そのためさまざまな抗がん剤が開発され、いろいろな組み合わせで試され、それぞれの効果が研究発表されてきました。
1970年代には、CMF療法が生まれました。乳がんの患者さんにC、M、Fの組み合わせで点滴をすると生存率が高くなることが証明され標準治療となりました。CMFは4週ごと6クール(6カ月間)やれば十分なこともわかりました。
80年代半ばになって、3週ごと4クールのAC療法はCMF療法と同じ効果であることが証明されて、CMF療法と並ぶ標準治療となりました。
その後、AやEの入った治療(CAF・CEF・FAC・FEC療法)は、CMF療法よりも生存率が高くなることが証明されたので、98年以降はアントラサイクリン系の治療が推奨されています。
タキソールやタキソテールという新しい抗がん剤を、効果の証明されているAC療法に追加して使ってみたところ、生存率が向上しました。現在、リンパ節転移の数が多いなど、予後の悪い患者さんに関してはAC-T療法が行われるようになっています。
最近の傾向としては、CMF療法やAC療法はだんだん使われなくなってきて、アントラサイクリン系の治療、特にアメリカでは先述したACにタキサン系を加えた療法、ヨーロッパではFEC療法が中心に、日本ではこれらとTC療法が行われています。
抗がん剤治療のことを「化学療法」といいます。英語の「ケモテラピー」、格好つけると「キモセラピー」の翻訳です。
抗がん剤やホルモン療法、分子標的薬も含めた薬物療法全体のことを「補助療法」と呼びます。英語でいう「アジュバントテラピー」の訳で、効果を高める治療という意味です。
この抗がん剤担当医師のことを英語で「メディカルオンコロジスト」といいます。「オンコロジー」とは腫瘍学、がんの学問です。メディカルは医学とか内科という意味。つまり「腫瘍内科医」といいます。ときには内科医ではなく外科医が抗がん剤を使う場合もあります。このときは自分を「化学療法医」と呼びます。
皆さんが呼ぶときは「抗がん剤」や「抗がん剤の先生」で結構です。
ホルモン療法にはどのようなものがありますか?
乳房は女性ホルモンで成長するので、乳がんの約3分の2も女性ホルモンを栄養にして成長します。そのような乳がんはホルモンを取り込む受容体をもっています。これをホルモン受容体陽性といいます。そこでホルモン受容体陽性乳がんのうち、遠隔再発の危険性が高いものに対して次のようなホルモン療法が行われます。
- 永久的卵巣機能抑制
- ホルモン療法の薬がなかったころは、閉経前女性の卵巣を切除したり卵巣に放射線をかけたりしました。効果が永久的で治療費は安くあがります。
- 一時的卵巣機能抑制
- 今は注射で卵巣の機能を抑えます。脳の下垂体(下に垂れているおちんちんのようなところ)から、卵巣の黄体(卵の黄身のようなところ)を刺激するホルモンが出ます。これを黄体(ルテイン)ホルモン刺激(リリース)ホルモンといって、頭文字でLHRHといいます(また頭文字だ)。LHRHを抑えれば卵巣の機能も抑えられます。これをLHRHアゴニスト(エゴイストに似てますね)と呼びます。商品名はゾラデックスまたはリュープリン。月に1回、あるいは3カ月に1回、2年間皮下注射します。効果は一時的ですので使用を中止すれば妊娠も可能でしょう。ゾラデックスは針が太いので、私は打つときに局所麻酔をします。
- 抗女性ホルモン剤
- フライフィッシングを知ってますか。虫に似せた疑似餌(にせの餌)に食いついた魚を釣り上げます。乳がんにも女性ホルモンと似た構造のにせホルモンを与えると、間違えて取り込んで餓死してしまいます。にせの女性ホルモンであるノルバデックス(一般名タモキシフェン)またはフェアストンを毎朝1回、5年間内服します。
- アロマターゼ阻害剤
- 閉経後は卵巣から女性ホルモンは出なくなりますが、かわりに副腎(腎臓の上についているデベソ)から出るアンドロゲンという男性ホルモンを、乳房にあるアロマターゼという転換酵素が女性ホルモンにかえて利用しています。乳がんもこの女性ホルモンで成長するのです。そこで閉経後乳がんにはアロマターゼの働きを抑える薬を使います。アリミデックスまたはアロマシンを毎朝1回、5年間内服します。
補助療法による更新期障害
地球上のあらゆる生物は生殖年齢が終了したら死ぬようにテロメアの長さが設定されています。しかし人間だけは子育てのために閉経後も生き続けるようになりました。その代償として得た苦しみが更年期障害です。
脳は自分の思い込みと異なることが生じるとパニックを起こします、たとえば、車の中で本を読んでいると乗り物酔いします。身体の平衡感覚は耳の三半規管と目の両方で保たれています。体の揺れと視覚の揺れにずれが生じると脳は混乱して吐き気を催すのです。
同じようにホルモン環境の変化によって脳が混乱して起きるのが、更年期障害なのです。閉経前のあなたの身体は女性ホルモンによってコントロールされています。しかし閉経後は副腎からの男性ホルモンに変わります。身体のホルモン環境は180度変化するのに、脳はそれについてこられず、女性ホルモンを出すように指令し続けるので身体は悲鳴をあげるのです。
閉経前女性にLHRHアゴニストと抗エストロゲン剤を投与すると、完全な閉経状態になります。また抗がん剤によっても多くの女性が閉経します。こうした急激な閉経は、徐々に女性ホルモンが減っていく自然閉経とくらべて、更年期症状が強く出やすいのです。
まず男性化するということはメタボ化するということです。増えた内臓脂肪がどんどん燃焼しますので、カーッとのぼせて、だくだく汗をかきます。顔色は黒ずんでいらいらします。心もアンバランスになって鬱になり不眠になります。
通常の更年期障害ならホルモン補充療法(頭文字でHRT)をします。しかしこれは乳がんに栄養を与えていることになるので危険です。昔から婦人薬とか血の道の薬といわれている漢方薬は、効く人には効きますが、合わない人もいます。鬱状態が強い人は抗鬱剤(SSRI)が有効という報告もあります。
ホルモン剤をかえてみるのもいいでしょう。ノルバデックス(タモキシフェン)、トレミフェン(フェアストン)、アナストロゾール(アリミデックス)、エキセメスタン(アロマシン)の4つの範囲で変更しても著しく効果が落ちることはありません。
タモキシフェンは子宮体がんになる?
子宮の内膜は月経のたびに増殖を繰り返しているのですから、テロメアは消耗します。つまりがんになりやすい場所です。にもかかわらず閉経前に子宮体がんが少ないのは、月経によって内膜ががん細胞ごと毎回リニューアルされるからです。
内分泌療法は月経を止めるのですから、がんが内膜に定着しやすくなります。しかし子宮体がんも女性ホルモンを栄養にするので、同時にがんの成長を止めていることになります。
そのため子宮体がんの発生率はたいして増えません。1万人に2人が16人になるといえば8倍になったと感じるかもしれませんが、増えたといっても1000人に1人か2人です。それに対して遠隔再発する人が3人いれば1人の命を救えるのです。
タモキシフェンによるホルモン療法中、子宮体がんの組織検査を勧める婦人科医もいます。これは子宮の中を小さなスプーンでこそぎ取る検査です。苦痛を伴いますので、症状がなければ腟の中から見る経腟超音波検査で十分です。子宮内膜が異常に厚くなっているときだけ、組織検査を受ければよいでしょう。
なお、抗エストロゲン剤(タモキシフェンやフェアストン)のほかの副作用には、静脈血栓症があります。足や肺の血管が詰まったりすることがまれにあるので、過去にそういう病気をしたことがある人には使用できません。
抗エストロゲン剤には次のような副産物もあります。
- 対側乳がんが3分の1減ります(反対側が乳がんになる確率は浸潤がんで2%、非浸潤がんで16%)
- 心臓病死亡の減少
- 骨粗鬆症の予防
私ならホルモン治療の効く、比較的進行している乳がんには、5年ではなく10年の内服を勧めます。
術前抗がん剤と術後抗がん剤、いいのはどっち
乳がんは手術法によって生存率は変わらない、補助療法によってのみ変わる、ということは理解できましたね。それならば抗がん剤をなるべく早く、つまり手術の前に使ったほうが生存率が高くなるのではないかと思うのは当然です。そこでくじ引き試験が行われました。その結果、術前抗がん剤と術後抗がん剤で生存率は変わりませんでした。
ただがんが大きかったり、リンパ節転移が明らかな場合は、術前に抗がん剤をします。
がんや腫れていたリンパ節が小さくなるのを観察すれば、効いているかどうかの判定ができるからです。まったく効いていないかむしろ大きくなるようなときはほかの抗がん剤に変えることもできます。全摘といわれていたのに、がんが小さくなったおかげで温存が可能になることもあります。
しかし、リンパ節転移があるといわれても実際に取ってみたら27%の人には転移がなかったという報告もあります。がんが大きくても、取ってみたらすごくおとなしいがんだったということもあります。その場合、術前の抗がん剤はやりすぎということになります。
温存療法を受けたくて術前抗がん剤をしても小さくならないときもありますし、小さくはなったけれどあちこちに散らばっていて、結局は全摘となることもよくあります。
できれば抗がん剤を使いたくないと思っているなら、まず手術をして病理結果の総合判定を見てから決めてもいいでしょう。
術前と術後で抗がん剤の種類を変えたほうがいいかという問いには、ほとんどの医師が変える必要はないと答えています。
術前抗がん剤ではなく術前ホルモン療法ではだめかと、聞かれることもあります。ホルモン療法の効くタイプなら抗がん剤と同等の効果があるはずだからです。しかしホルモン療法は効果があらわれるまで時間がかかるので一般的ではありません。ただし手術まで相当待たされるときは安心のために飲んでおいてもいいかもしれません。
抗がん剤の副作用はなぜ起こる
がんはテロメアの複製酵素テロメラーゼをもった永遠の修復細胞だといいましたね。抗がん剤はその細胞分裂を止める薬です。もちろんがんにいちばんよく効きますが、身体のほかの部分でも細胞分裂が盛んな組織は障害を受けます。
皮膚のやけどは治るのに数週間かかりますが、口の粘膜は熱い味噌汁でやけどをしても、翌日にはほとんど治っていますよね。つまり消化管の粘膜は細胞分裂が盛んなのです。したがって抗がん剤の副作用も出やすい。消化管が障害を受けると吐き気や下痢、食欲不振が起きます。吐き気の予防には制吐剤と呼ばれる薬(5-HT3受容体拮抗剤)とステロイド剤の併用が効果的です。
男は1日ひげをそらないと無精ひげでむさ苦しくなります。つまり髪の毛や眉毛、まつ毛といった体毛も細胞分裂が盛んです。毛根が障害されると、脱毛が起きます。特にAやEといったアントラサイクリン系の薬は100%抜けます。治療が終了すれば回復しますので、それまでの間ヘアウイッグ(かつら)やバンダナなどをうまく利用するといいでしょう。まつ毛が生えてきたら「ラティース」という薬を塗ると早く伸びます。
血液をつくる骨髄も障害を受けます。血液は酸素を運ぶ赤血球、バイ菌をやっつける白血球、血を止める血小板からできています。赤血球が減ると貧血になります。立ちくらみに注意しましょう。血も止まりにくくなりますので抜歯をするのはあとにしましょう。何より白血球が減ると免疫力が落ちて風邪をひきやすくなったり、傷が化膿しやすくなったりします。そこで白血球を増やす薬(G-CSF製剤)や細菌を退治する抗生物質が用いられます。
卵巣も細胞分裂が盛んです。そのため抗がん剤で閉経することがあります。特にC、つまりシクロフォスファミド(エンドキサン)という抗がん剤でよく起きます。若いほど閉経しにくく、閉経年齢に近いほど閉経しやすいのです。
CMFを使うと、20代で約20%、30代で30%、40代で80%以上が閉経しました。
CAFやCEFの場合は、20代で閉経する人はほとんどなし、30代で10〜25%と少なくなりましたが、40代ではやはり80%以上閉経しました。
ACでは、20代で閉経する人はほとんどなし、30代で13%、40代で約60%でした。
乳がんの予後因子
子どもが試験で0点を取ってきてもおたおたしてはいけません。最終的に通信簿をもらってその総合判定で出来不出来を判断すればいいのです。乳がんも1つや2つ悪い結果が出てもあわてないで、病理結果の総合判定を待ってから今後の方針を決めてください。
人間は多面体です。言葉は乱暴でも心はやさしいかもしれない。顔は銀行員のように真面目そうでも大悪人かもしれない。同じようにがんをいいか悪いか評価するときには、いくつものポイントがあります。それを予後因子といいます。「予後」とは病気の経過のことです。乳がんのこれからの経過を左右するいくつかの条件を予後因子といって、手術で取った組織を病理医が顕微鏡で見て判定します。
- リンパ節転移
- リンパ節は乳房と全身との国境につくられた関所です。そこにがんがあったということは、すでにがんが全身に回った確率が高くなります。
- がんの大きさ
- 手術前に病期を決めますがそれは手でさわって決めたのでいいかげん。これは病理医が顕微鏡で測った正確な大きさです。大きいほうがたちが悪いのです。
- リンパ管・脈管侵襲
- これが陽性ということはがんの周囲のリンパ管や静脈内にがん細胞があるということで、「リンパ行性転移」や「血行性転移」の可能性が高いのです。
- グレード
- 悪い細胞はふぞろいで並び方もでたらめ。これを顕微鏡で見てIからIIIまで分類します。数字が大きくなるほどがんの顔つきが悪く転移しやすいのです。
- HER2
- 転移しやすくなるがん遺伝子のことです。0~+3のうち+3だけが陽性。+2のときは灰色なのでFISH法という再検査をします。
- ホルモン受容体
- ER(エストロゲン受容体)とPgR(プロゲステロン受容体)があります。これも0~+3まであってどちらか少しでも+なら陽性です。乳がんは乳腺同様女性ホルモンを栄養にして発育しますが、なかには女性ホルモンがなくても発育するたちの悪いものがあります。陽性はたちがよくてホルモン療法もよく効き、陰性はたちが悪くホルモン療法も効かないのです。
- Ki67
- がんの増殖能、大きくなるスピードです。10%まではゆっくり、30%までは中等度、30%より上はスピードが早いということになります。
乳がん治療の新憲法
小泉元首相じゃありませんが、乳がんもいろいろ、薬物療法もいろいろ。どんな乳がんにどんな補助療法をするのが最善なのかを知ろうと思ったら、乳がんのタイプ別にあらゆる組み合わせの補助療法を試してみないといけません。これには気が遠くなるほどの年月が必要です。そこで2年に1回、スイスのザンクトガレンという街に世界中の乳がん専門医が集まって乳がんの国際会議が開催されます。いくら議論しても平行線の場合、最後は多数決で決めます。
2005年の時点では乳がんをリスク分類することになりました。
乳がんの予後因子がどれも引っかからなければ低リスク、1つでも当てはまれば中リスク、さらにたくさん当てはまるなら高リスク。高リスクなら抗がん剤とホルモン療法、中リスクならそのいずれか、低リスクなら何もしないといった案配です。
しかし2013年のザンクトガレンではホルモン受容体とHER2とKi67の値によって以下の5つに分類しました。
- 1 ホルモン受容体陽性のゆっくりがんタイプ
- ホルモン受容体陽性でHER2が陰性、Ki67が低いとき。ホルモン療法単独。リンパ節転移が多く、がんが大きいときは抗がん剤も考慮する。
- 2 ホルモン受容体陽性のスピードがんタイプ
- ホルモン受容体陽性でHER2が陰性だが、Ki67が高値のとき。抗がん剤とホルモン療法。
- 3 ホルモン受容体陽性・HER2陽性タイプ
- ホルモン受容体陽性とHER2が陽性のとき。すべての治療法が効果的なので、抗がん剤と分子標的薬(ハーセプチン)とホルモン療法。
- 4 ホルモン受容体陰性・HER2陽性タイプ
- ホルモン受容体が陰性でHER2が陽性のとき。分子標的薬が有効なので、抗がん剤と分子標的薬(ハーセプチン)。
- 5 トリプルネガティブタイプ
- ホルモン受容体(ER、PgR)とHER2の3つが陰性のとき。ほかに治療法がないので抗がん剤単独。
オンコタイプDX
がんのタイプによって、治療方針が決まることは理解できましたか。
抗がん剤が効かなくて副作用が少ないホルモン療法がよく効く、といわれたら多くの人は「ラッキー!」といってホルモン療法単独治療を受けます。
分子標的薬がよく効くといわれたら、やらないと損です。やらなければ遠隔転移の可能性が高く、やれば6割以上の確率でがんが消えてしまうからです。
トリプルネガティブといわれたら、ほかに治療法がないわけですから、しぶしぶ抗がん剤を受けるでしょう。
問題はホルモン受容体が陽性のゆっくりがんでも、リンパ節転移やそのほかの予後因子が陽性でホルモン療法と同時に抗がん剤を勧められたときです。本当に抗がん剤は必要なの、ホルモン療法だけじゃだめなの、と感じるでしょう。
またその逆で、ホルモン受容体が陽性のスピードがんでも、そのほかの予後因子がどれもよくって、ホルモン療法だけじゃだめなの、と感じたときです。
さあ、こんなときはどうしましょう。主治医に決めてもらいますか?
なに!主治医が信用できないって!?それをいっちゃあおしまいだよ。
こんなときはオンコタイプDXという検査があります。
主治医に頼んで、病理検査に出したあなたの乳がん組織の一部を外国の検査会社に出すと、数週間で結果が出ます。再発に関連する21種類の遺伝子を調べて、将来の再発の危険性と抗がん剤をやったときの効果が予測できるのです。
対象は次のとおり。
- ホルモン受容体が陽性でリンパ節転移もないのに抗がん剤を勧められたとき。
- 閉経後でホルモン受容体が陽性でリンパ節転移があって、それでも抗がん剤をやりたくないとき(閉経前の方はまだ長い人生が残っているのですから抗がん剤を受けてください)。
低リスクといわれたら抗がん剤を受けてもあまりメリットはありません。
高リスクといわれたら抗がん剤を受けたほうがいいでしょう。
ただし保険はききませんので数十万円という自己負担が必要です。
補助療法をするかどうかは自分で決めよう!
抗がん剤、ホルモン療法、分子標的薬による治療を補助療法といいます。
補助療法を行うかどうかは、次の3つの因子によって決定します。
- 補助療法をしない場合の予後(治療の経過)がどうなるか?
- 補助療法によって予後がどの程度改善されるのか?
- 補助療法に重大な副作用があるか? その頻度は?
ほとんどの乳がんは遠隔転移を起こすと根治は不可能です。そのため遠隔転移の予防ための補助療法が大切なのです。遠隔再発率が高い乳がんで、補助療法の効果が高く、その副作用の頻度が低ければ誰もが補助療法を受けるでしょう。その反対に、遠隔再発率が低いにもかかわらず、補助療法の効果が低い場合や、重大な副作用がある場合は、誰も補助療法を受けないでしょう。
ここで一例をあげて説明しましょう。補助療法をしない場合の予後は、腋窩リンパ節転移、腫瘍の大きさ、組織学的グレード、ホルモン受容体、HER2、Ki67そして脈管侵襲によって決まると既述しました。たとえばリンパ節転移がなく腫瘍の大きさが3cm以上のときの10年遠隔再発率は20~50%です。この方が補助療法を行えば10年遠隔再発率が2分の1改善することが判明しています。ということは遠隔再発率を20%としたときには、次のようになります。
- 補助療法によって命が助かる人の割合は、20%の2分の1の10%。
- 補助療法をやっても助からなかった人の割合は、20%の2分の1の10%。
- 残りの80%は補助療法をやらなくても遠隔再発しなかった人たちです。
つまり「やって得した群」は10%、「やって損した群」は90%です。
遠隔再発率を50%としたときには、「やって得した群」は50%の2分の1で25%、「やって損した群」は75%です。
この10~25%の「やって得した群」の確率と、重大な副作用の頻度(たとえば不妊になる確率が70%)を考え合わせて、あなたが補助療法に魅力を感じるかどうか、それが「補助療法をするかどうか」の決め手となるのです